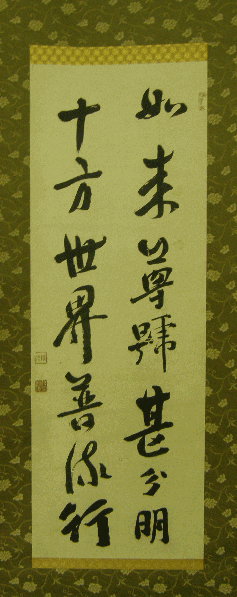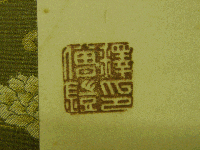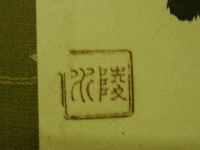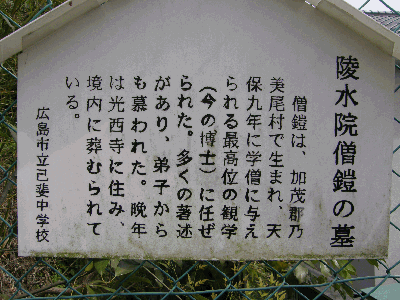勧学・僧鎧の墓
*光西寺と僧鎧
光西寺の
山門の前、脇の坂道を、約20数歩ほど登り、右に入ると
境外ですが、
墓地があり、
僧鎧の墓があります。

僧鎧は、加茂郡乃美尾村の出身で、
宗学を
修め
天保9年(1838年)に、
学林の勧学という地位を
任ぜられた方で、
広島市中区中島町の
善福寺の
住職をされましたが、晩年は、ここ、光西寺に住まわれ、天保11年(1840年)6月21日日に、
お亡くなりました。
70歳でした。
遺徳を慕う人達の
懇請があって、
境内(当時)に、葬られれました。
*「僧鎧」その生涯
生(1771年)~没(1840年)
僧鎧は、広島県加茂郡乃美尾村(現在は、広島県賀茂郡黒瀬町)で、進藤家の生を受けました。
25歳のころ(1796年のころ)、今の呉市で開かれていた、
僧叡の
私塾
・
石泉社で
宗学を修めました。
僧叡門弟名簿(石泉社「
門人帳」)では、百十人の名前の第2番目にその名が記されているそうです。
天保9年(1838年)に、勧学(学林の学階名)に昇進しました。
学林は、
浄土真宗本願寺派
の宗学の最高機関であって、その
学階は、
文政7年(1824年)に
本山直結の勧学(9人)を設け、
翌年、その下に、
司教(5人)・
主議(5人)・
助教(8人)・
得業(11人)が整えられ、学林の講義は、本講を勧学・
副講を司教・付講をその他の学位の者で努める形が敷かれました。
その学林において、僧鎧は、文政11年(1828年)に司教に進み、天保9年(1838年)に勧学に昇進し、翌年
年頭となり、
光西寺において、天保11年(1840年)に、亡くなられました。
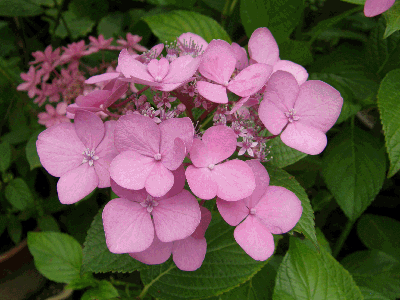
僧鎧は、
善福寺(今の 中区中島町)で、第14世
住職をされましたが、仏書・漢字に長じ、
多くの弟子もあり、また、著書も多くあります。
晩年は、当時はまだ隠寺
(かくれてら)だった光西寺に、住まわれました。
光西寺の
寺号が認められたのは、
僧鎧が亡くなった後の、明治12年(1879年)のことでした。
*僧鎧が残した書
僧鎧は、光西寺に書を残している。掛け軸は、傷みもほとんど無く、保存状態はいい。
以下に、掛け軸を紹介します。
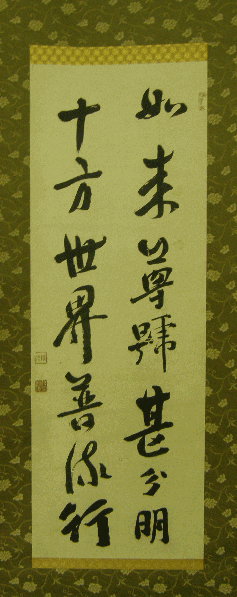
如来尊号甚分明
十方世界普流行
但有称名皆得往
観音勢至自来迎
《五会法事讃》の文
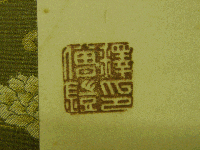
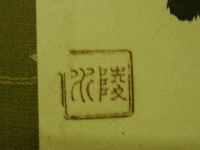
掛け軸の落款
「釈僧鎧」 「陸水」
書かれている文は、親鸞聖人の兄弟子にあたる聖覚法印の
著された「唯信鈔」について、引用されている経文等について注釈したものである
「唯信釥文意」の初めの3文の内、
法照禅師の
「五会法事讃」の言葉からです。
その言葉は、如来の尊号、
すなわち南無阿弥陀仏の御名は、
はなはだすぐれていて、よろずの衆生の
一人ひとりに、あきらかに分け与え届けられている。しかも十方世界に
あまねくひろまって念仏となって活動して、一切衆生を
たすけ導かれている。ということであるから、無碍光仏は、
智慧の光となって私たちのうえにはたらき、広大な
智慧である
本願の海に導き入れてくださるのである。
という意味です。
書の大きさ(書の部分) タテ 98cm ヨコ 33cm
書の落款も、写真(拡大しています)にしました。
僧鎧の著書には、「読助正釈間」「略述真宗義」「入出二門偈講録」2巻「大谷聖人本伝枢要」「第十八願成正記」「宿善論」等がある
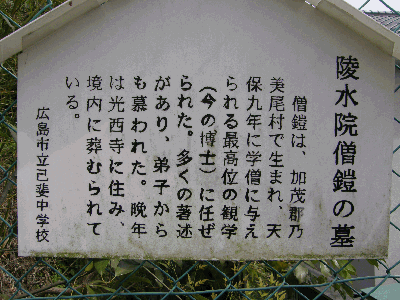
僧鎧の墓の側には、己斐中学校による案内説明板が、設置されている。
トップページへ
 僧鎧は、加茂郡乃美尾村の出身で、
僧鎧は、加茂郡乃美尾村の出身で、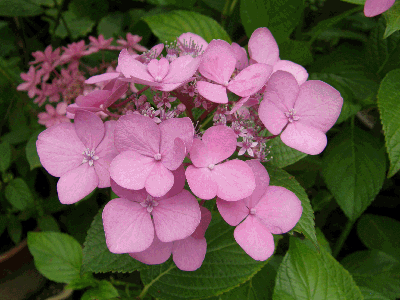 僧鎧は、
僧鎧は、