| 王羲之 蘭亭集序 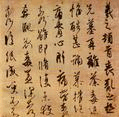 蘭亭記とも言う、浙江省紹興の西南二十七里蘭渚で王羲之(王逸少)は、当時の名士孫綽・謝安ら四十一人と祓禊、曲水流觴の宴を開いた。王羲之はその事を述べて「蘭亭集序」を作った。千古の名筆、その書は七代の孫の智永禅師が蔵していたものを、その弟子、弁才が蔵していた。唐の太宗がこの蘭亭集序を召し取って非常に愛重し、遂に自分と共に昭陵に葬る。真筆は唐末期の乱に陵が盗掘された後、その所在は不明になった。 永和九年、歳在癸丑。暮春之初、会于会稽山陰之蘭亭。集禊事也.郡賢畢至、少長咸集。此地有崇山峻嶺、茂林脩竹。又有清流激湍、映帯左右。引以為流觴曲水、列座其次。雖無絲絃管之盛、一觴一詠、亦足以暢敍幽情。是日也、天朗気清、恵風和暢。仰観宇宙之大、俯察品類之盛。所以遊目騁懐、足以極視聴之娯。信可楽也。 永和九年、歳癸丑に在り。暮春の初、会稽山陰の蘭亭に会す。禊事を修むるなり。.郡賢畢とく至り、少長咸集まる。此の地に崇山峻嶺、茂林脩竹有り。又清流激湍有りて、左右に映帯す。引いて以て流觴の曲水と為し、其の次に列座す。無絲絃管の盛無しと雖も、一觴一詠、亦以て幽情を暢敍するに足れり。是の日や、天朗かに気清く、恵風和暢する。仰いで宇宙の大えお観る、俯して品類の盛んなるを察す。目を遊ばしめ懐を騁する所以、以て視聴の娯を極めるに足りる。信に楽しむ可きなり。 夫人之相與俯仰一世、或取諸懐抱、悟言一室之内、或因寄所託、放浪形骸之外。雖趣舎萬殊、静躁不同、当其欣於所遇、暫得於已、快然自足,曾不知老之将至。及其所之既倦、情随事倦、情随事遷、感慨勝係之矣。向之所欣、俛仰之間、以為陳迹。尤不能不以之與懐。況脩短随化、終期於尽。古人云、死生亦大矣。豈不痛哉。 夫れ人の相與に一世に俯仰するや、或いは諸を懐抱に取りて、一室の内に悟言し、或は託する所に因寄して、形骸の外に放浪す。趣舎萬殊にして、静躁不同じからずと雖も、当其の遇う所を欣んで、暫らく已に得るに当っては、快然として自ら足り,曾て老の将に至らんとするを知らず。其の之く所に既に倦み、情事に随いて遷るに及んでは、感慨之に係れり。向の欣ぶ所は、俛仰の間に、以に陳迹と為る。尤も之を以て懐を興さざる能はず。況や脩短化に随って、終に尽くるに期するをや。古人云う、死生も亦大なりと。豈に痛ましからずや。 毎覧昔人興感之由、若合一契。未嘗不臨文嗟悼。不能喩之於懐。固知一死生為虚誕、斎彭殤為妄作。後之視今、亦猶今之視昔。悲夫。故列敍時人、録其所述。雖世殊事異、所以興懐、其致一也。後之覧者亦将有感於斯文。 昔人感を興すの由を覧る毎に、一契を合せたるが若し。未だ嘗て文に臨んで嗟悼せずんばあらず。之を懐に喩ること能わず。固に死生を一にするは虚誕たり、彭殤を斎しくするは妄作たるを知る。後の今を視るも、亦猶今の昔を視るがごとくならん。悲しいかな。故に時人を列敍して、其の述ぶる所を録す。世殊に事異なりと雖も、懐を興す所以は、其の致一なり。後の覧ん者も、亦将に斯の文に感有らんとする。 蘭亭集詩 ニ首の一 仰視碧天際 仰いで碧天の際を視る 俯瞰淥水濱 俯して淥水の濱を瞰る 寥閴無涯観 寥閴として涯観なく 寓目理自陳 目を寓すれば理自ら陳ぶ 大矣造化工 大なるかな造化の工 萬殊莫不均 萬殊も均しからざる莫し 群籟雖参差 群籟 参差たりと雖ども 適我無非新 我に適して新に非ざる無し 語釈:蘭亭==浙江省の山陰県にある. 際==はて. 瞰==下を見る 寥閴==「寥」は形無く,「閴」は静か,ひっそり.さびしい. 寓目==目を留めて見る. 理==万象の奥にある真理, 工==技術 萬殊==萬象が尽く相異なっている 群籟==多くの音楽,「籟」は笛, 参差==不揃いで多く集まっている 無非新==すべて清新な調子の音楽に聞こえる この日の参会者は四十二人,当時の名立たる名士が座にいた.四十歳を過ぎ,まだ中央官界の重鎮でありながら,会稽の地に隠棲して,風流自適に生活を楽しむ『謝安』がいた.王羲之の関与する琅邪の王氏と双璧をなす大貴族陳郡の謝氏の筆頭である.王羲之より十七歳の隔たりは無く五十歳を過ぎた王羲之が心を許す良き仲間でもあった.その弟の謝万も兄の傍に同席していた. 「玄言詩」の大家として一世を風靡した,道家の哲学にもとづいた詩人『孫綽』と,その兄,孫統が,この日,遊びに加わった,王羲之の子弟では,凝之・徽之・献之などが特に七男の献之は父王羲之と共に『ニ王』として世間から尊崇を以って崇めららている書の大家である. 王羲之・謝安兄弟・孫綽など十一人が四言・五言各一首を作り,十五人が四言・五言いずれか一首をつくった.詩の出来なかった十六人は罰といて大きな盃,三杯の酒を飲まされた.その中に献之がいた,彼はこの日インスピレーションが涌かなかった.雅詩の宴席で「伯梁体」など即席で求められる場合,平常「韻」を授けられる,即席で一詩書く習慣が身に着いているが,佳詩を作ろうと思えば,思うほど佳作が出来ない. 王羲之は,この日,参列者二十六人の詩を纏めて一書に編み,その前後に王羲之自身と孫綽の序を配して『蘭亭集』と名ずけた.三百二十四字からなる蘭亭序は,前半,春の喜びと遊宴の楽しさを讃える言葉で埋め尽くされている.後半に至ると一変し調子が改まる.人生の悲哀から「荘子」的な死生の価値観の達観は所詮言う所の虚偽にすぎず,時の流を,ありの侭に見据え人生をそのまま述べる. 文選李善注の性質より抜粋 あらゆる評價は當時の政治的、經濟的、社會的な情況及び各自の意向・性質などに強く影響支配されることは免れ難く、絶對的に客觀的な評價というものは存在し難い。勿論、傑出した哲人や偉人が一定の規準を創り上げ、世俗の人々を導くことは必要不可缺な面もあり、偶像化や神聖化が必ずしも意義のないことではない。しかし、學問が「眞」「善」「美」を追究するものである以上、やはり作り上げられた結果である偶像を顯彰する方向ばかりではなく、先ず本來の姿である實像はどのようなものであったかを明確にした後、それが如何なる目的の下に、どのような過程を經て偶像として形成されていったかを解明することが非常に重要である。 例えば、唐初、太宗李世民は王羲之を愛好崇拜するあまり、『晉書』の改修を命じ、自ら論贊を表して、「書聖」王羲之を作り上げた。また所在不明だった、眞贋の紛らわしい蘭亭序帖を發掘入手し、褚遂良に鑑定評價させ上、彼の『右軍書目』に著録させて第一の「名品」に仕立て上げた。玄宗朝には劉餗『隋唐嘉話』・何延之『蘭亭記』などといった傳奇物語が創作され、「書聖」王羲之が「神助」を得て書き上げたこの「神品」は太宗とともに昭陵に埋葬されたとまことしやかに宣傳された。その結果、ますます神秘性を帶びてきた「蘭亭帖」は模本までもが珍重され、寶物となっていった。宋代には遂に王羲之と蘭亭序に關する一大事典の如き『蘭亭考』なるものまでもが編纂され、確實に偶像化され、神聖化されていった。太宗李世民の王羲之を賞揚する意向は見事に成功し、王羲之と蘭亭序帖は絶對的なものに昇華され、神格化されたのである。 その結果、現代に至るまで「書聖」王羲之は偶像化されたまま、その實像は全く見失われてしまい、「神品」蘭亭序帖は眞贋不明の状態のまま、絶對的な傑作として書道界に君臨し續けている。また『文選』の序部に採録されていなかった「蘭亭序文」までもが後世、一般には殆ど何ら疑念を挾まれることなく、無批判に「眞寳」と認定され、『古文眞寶』に收録された後は、すっかり不朽の名文と認定されてしまっている。 このような偶像化を見過ごしてしまうと、遂には例えば『晉書』王羲之傳の「我卒當以樂死」は、「私は結局快樂の中で死ぬのだろうな」という不可解な解釋のままに何の疑問も抱かれることなく放置され、「眞意」を追究する姿勢をすらすっかり忘却してしまう結果に終わるのである。これは前後の文脈から見て、當然「私は最後はきっと藥で死ぬだろうな」と解釋すべきものである。 このように絶對視され、偶像化されたままの状態を見過ごしてしまうと、「書聖」王羲之や蘭亭序帖がそうであるように、「李善註文選」の實態、實像が全く見失われてしまう虞があるのみならず、ひいては文選學全體の研究を誤った方向に導く危險性すらある。そこで小論は現存の「李善註文選」を稍しく丁寧に檢討分析することを通じて、制作當初の實態及び實像の究明に努め、「李善註文選」の成立過程及び位相を明確にしたい。 Copyright(C)1999-2004 by Kansikan AllRightsReserved thhp://www.ccv.ne.jp/home/tohou/rannteiki.htm 石九鼎の漢詩舘 |